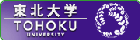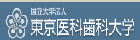◇ 院長紹介
院長略歴
院長挨拶
歯学部を卒業して保存科に入りましたが、翌年東京医科歯科大学の口腔外科に移りました。
専門は口腔外科ですが、1年目の保存科時代に受けた影響が大きく、歯をなるべく抜かずに残すことを治療の大前提としています。
趣味は、現在天体観望と風景写真を撮ることくらいになってしまいました。音楽はクラシックと70年代と80年代の歌謡曲を聴いています。
歯学部に入るまではクラシックギターを弾いていましたが、大学の実習で爪を切れと言われ、以後ほとんど弾かなくなりました。
理学部時代、趣味は数学と言えるほど一生懸命勉強していました。今でも面白いと思っていますが、話すと相手が退くので喋る相手がいません。
本来天文学への興味から量子力学と一般相対論を勉強しようと、関数解析学と微分幾何学を専門に選びましたが、数学に魅了されて以来、物理学には手が回りませんでした。
流山市歯科医師会のホームページ製作に携わってからかなりの年月が過ぎましたが、自分の診療所のホームページの製作は遅々として進みませんでした。これからはゆっくりと仕上げていきたいと思います。
最近読んだ本
面白かった本
- 養賢堂の「解析学概論」(林五郎・御園生善尚著)
東北大の先生が書かれた昔の本で、今は絶版になっています。この本で初めてリーマン積分の定義を知り、高校時代良く判らなかった積分学の意味が分かりました。ニュートンとライプニッツが証明した微積分学の基本定理の便利さは、積分計算の大変さから意義が分かります。 - 裳華房の数学選書1「線形代数学」(佐武一郎著)
有名な、佐武の「行列と行列式」の改訂版で素晴らしいの一言。昔の「行列と行列式」の類似書は円錐曲線の分類を示すことに重きが置かれていました。高校数学の改訂で大学の数学の教科書も内容が変化している感じです。 - 裳華房の数学選書4「ルベーグ積分入門」(伊藤清三著)
入門とありますが、決して入門書ではありません。しかし、吉田耕作の洋書「Functional Analysis」を読むには必要不可欠でした。 - 培風館の新数学シリーズ23「ルベグ積分入門」(吉田洋一著)
これこそが入門書で、多くの大学で使われている親切、丁寧な本です。 - 裳華房の数学選書5「多様体入門」(松島与三著)
これも入門書ではありません。類似タイトルの邦書では一番難しいかも。この中の「88ページの問1」と「90ページの問2」が証明出来ないまま、反証も出来ずにいます。どの教科書でもそうですが、所々、添え字に間違いが幾つかありました。 - 岩波書店の「現代数学概説Ⅰ」(彌永昌吉・小平邦彦著)
第1章の集合論が素朴集合論の解説としては最高かと。第4章の束論も良かった。 - 岩波書店の「現代数学概説Ⅱ」(河田敬義・三村征雄著)
前半の位相が頭の中で纏めるのに最高ですが、後半の測度は難しく、加法的集合族の生成で超限順序数を用いるを見て、早々と読むのを止めました。 - 岩波書店の「集合・位相入門」(松坂和夫著)
入門書です。集合と位相について、易しく丁寧に書かれています。 - 共立出版の共立数学講座24「代数学」(成田正雄著)
代数学を専門にしない人に向いてます。拡大体の話から有名な定理(5次方程式以上では根の公式がないという定理です。アーベルとガロアが独立に証明しました)まで解り易いです。同じような厚さですが、演習書とセットになっている朝倉出版の近代数学講座「現代代数学」(服部昭著)は難し過ぎて、手を出さない方が無難です。と言っても今は絶版になっているかもしれません。これよりは岩波の「現代数学概説Ⅰ」の方が楽です。'60年代後半から'70年代に数学科の学生は、このような骨の折れるテキストを読みこなしていたのかと思うと頭が下がります。ちなみにアーベル賞の賞金額は1億円と、ノーベル賞並です。有名なフィールズ賞の賞金額は低く、名誉賞と考えるべきです。 - 更に追加していきたいと思います。
- 晶文社の「脱病院化社会」(イヴァン・イリッチ著、金子嗣郎訳)
自分の中にある健康の概念がひっくり返されました。 - 岩波新書「歴史とは何か」(E.H.カー著、清水幾太郎訳)
たくさん読んだマルクスやエンゲルス、レーニンのどの本よりも歴史観を鍛えられました。 - 弘文堂法学選書11「医療行為と法」(大谷実著)
この本を読んでから法律に興味を持ち影響をうけました。 - 弘文堂の法律学講座双書「憲法」(伊藤正己著)
最高裁判事にまでなられた方の本です。初心者には分かり易いです。 - 弘文堂の法律学講座双書「民法総則」(四宮和夫著)
四宮先生は亡くなられなりましたが、裳華房の「ルベーグ積分入門」並の絶品だと思いました。 - 有斐閣双書の「民法第2巻~第7巻まで」
無味乾燥という噂と違い、この双書民法は面白く、とりわけ物権法と第7巻にある不法行為が良かったです。 - 筑摩書房の現代法学全集20Ⅱ「不法行為法」(幾代通著)
前書では物足りなく、それで買ったのがこの本ですが、幾代先生も亡くなられました。 - 文春文庫「フロイト先生のウソ」(ロルフ・デーゲン著、赤根洋子訳)
マスメディアの作り上げた嘘の数々がウソだと分かります。とりわけ二重人格のウソが。 - 中公文庫の「日本の歴史」 第6巻から26巻まで
20巻「明治維新」と21巻「近代国家の出発」が特に感動しました。 - 中公文庫の「世界の歴史」 第6巻から第16巻まで
第8巻「絶対君主と人民」と第10巻「フランス革命とナポレオン」が良かったです。30年戦争によりフランスがスペインから覇権を奪い、ナポレオン時代に絶頂に達した過程が分かります。 - 集英社新書「英仏百年戦争」(佐藤賢一著)
この百年戦争が、元々フランスの内戦から始まり、その過程で英国が征服され、全領主がフランス人に置き換えられた事を知りました。可愛そうなのはジャンヌ・ダルクに率いられたフランス人ではなく、とうの昔に攻め滅ぼされた英国貴族だったようです。 - 岩波新書447「歴史とは何か」(E.H.カー著、清水幾太郎訳)
追加:上にも書きましたが、更に追加します。随分前に読んだ本ですが、それまでに読んだ沢山の「歴史とは何か」といった類書のどれよりも感銘を受け、影響を受けた本です。これが1962年に出版されていたのも驚きでした。もっと早く読んでおけば良かったとどれだけ後悔したことか、今は昔の話です
1971年に初めて大学に入学し、左派系の大学教授の講義を受けて翻弄されましたが、思想的に脆弱な自分の当然の報いかもしれません。この本を1971年に読んでいたら、正直、人生が大幅に変わっていたと思います。
◇ スタッフ紹介
スタッフ挨拶
スタッフ写真